

今年4月から始まった新しい制度、「出生後休業支援給付金」について、従来の制度と比較しながら、その目的や条件、そして男性の育児参加の重要性について深掘りしていきましょう!
育児休業給付金の基本と課題



まず、今回の新制度を理解するために、従来の育児休業給付金の基本的な内容を確認しておきましょう
従来の育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して、以下の内容で支給されていました。
•育児休業開始から180日目まで: 給料の67%
•181日目以降: 給料の50%
これにより、育児休業中の経済的な不安を軽減する役割を果たしてきましたが、収入が減少してしまうことは、育休取得をためらう理由の一つとなっていました。特に男性の場合、「収入が減少してしまうため」が育休を取得しない最大の理由として挙げられています
新制度「出生後休業支援給付金」とは?給付金がまさかの80%に!



そんな中、今年4月から新たに創設されたのが「出生後休業支援給付金」です。
これは、育児休業給付金に上乗せされる給付金で、ある条件を満たすと、育児休業給付金と合わせて給料の80%相当が支給されるという画期的な制度です。
さらに重要な点として、この給付金は非課税であり、育児休業中は社会保険料も免除となるため、手取りベースで考えるとほぼ100%になる可能性があります 。これは、育児休業中の収入減という不安を大きく解消する、まさに「神」のような制度と言えるでしょう。



しかし、「出生後休業支援給付金」を受け取るためには、いくつかの条件があります。
「出生後休業支援給付金」をもらうための条件



では、「出生後休業支援給付金」を受け取るためには、どのような条件があるのでしょうか?
<出生後休業支援給付金」をもらうための条件>
•パパ: 子どもが生まれてから8週間以内に、14日以上の育児休業を取得する必要があります
•ママ: 産後休業後8週間以内に、14日以上の育児休業を取得する必要があります
つまり、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得すれば、2人ともこの給付金を受け取ることができます。手取りほぼ100%相当となるのは、最大で28日間です。
ただし、配偶者が産後休業中の場合や、自営業者・フリーランス・無職の場合などは、本人の育児休業取得のみで要件を満たすことができます。



このように、取得しやすいように条件が緩和されている点もポイントです!
なぜ今、男性の育児参加が重要視されるのか?
国が給付金を増やすなどしてまで男性の育休取得を促進する背景には、少子化対策という大きな目的があります。研究によると、夫の休日の家事・育児時間の長さは、第二子以降の出生率と比例することが分かっています 。
さらに、育休を取得した男性は、その後も家事・育児に積極的に関わる傾向があり、男性の家事・育児時間の長さは夫婦の愛情にも影響するというデータもあるそうです。まさに、産後は夫婦の絆を深めるかどうかの運命の分かれ道と言えるかもしれません。
また、産後のママの体は、全治12ヶ月の交通事故にあったような状態と言われるほど大きなダメージを受けています1 。産後すぐから3ヶ月程度は、産後うつなどのリスクも高まるため、パパによるママの心身のケアは非常に重要な任務なのです
これからの時代、男性も育児へ積極的に参加を!
今回の新しい「出生後休業支援給付金」は、経済的な不安を軽減し、男性が育児に積極的に参加するための大きな後押しとなるでしょう。限られた期間ではありますが、手取りがほとんど減らずに育児に専念できる制度を利用しない手はありません。
出産を控えているご夫婦はもちろん、これから家族が増える予定のある方は、ぜひこの新しい制度について理解を深めてください。男性の育児参加は、子どもの成長にとってかけがえのないものであり、夫婦の絆をより一層深める機会にもなります。この機会に、夫婦でしっかりと話し合い、共に育児に取り組むことを考えてみてはいかがでしょうか。



いつもは資産運用についてまとめていますが、今回のブログ記事を通じて新しい育児休業給付金制度への理解を深め、これからの育児について考えるきっかけとなれば幸いです。


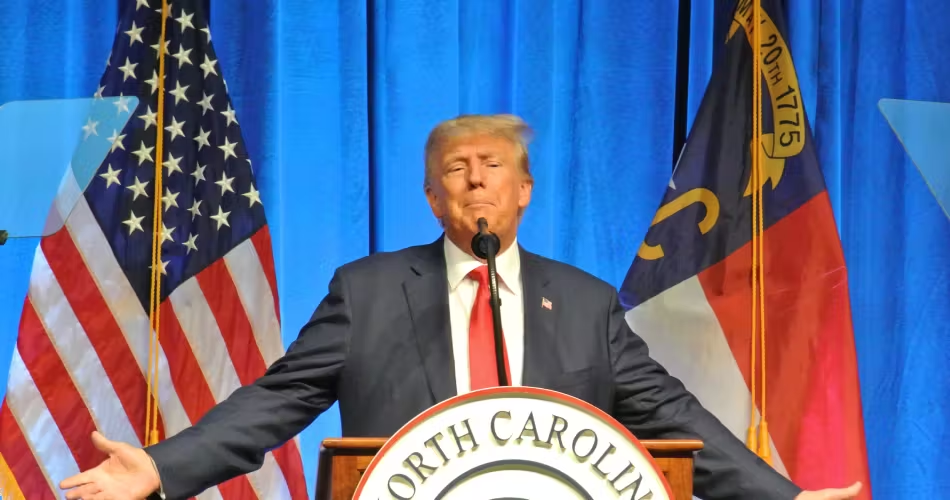
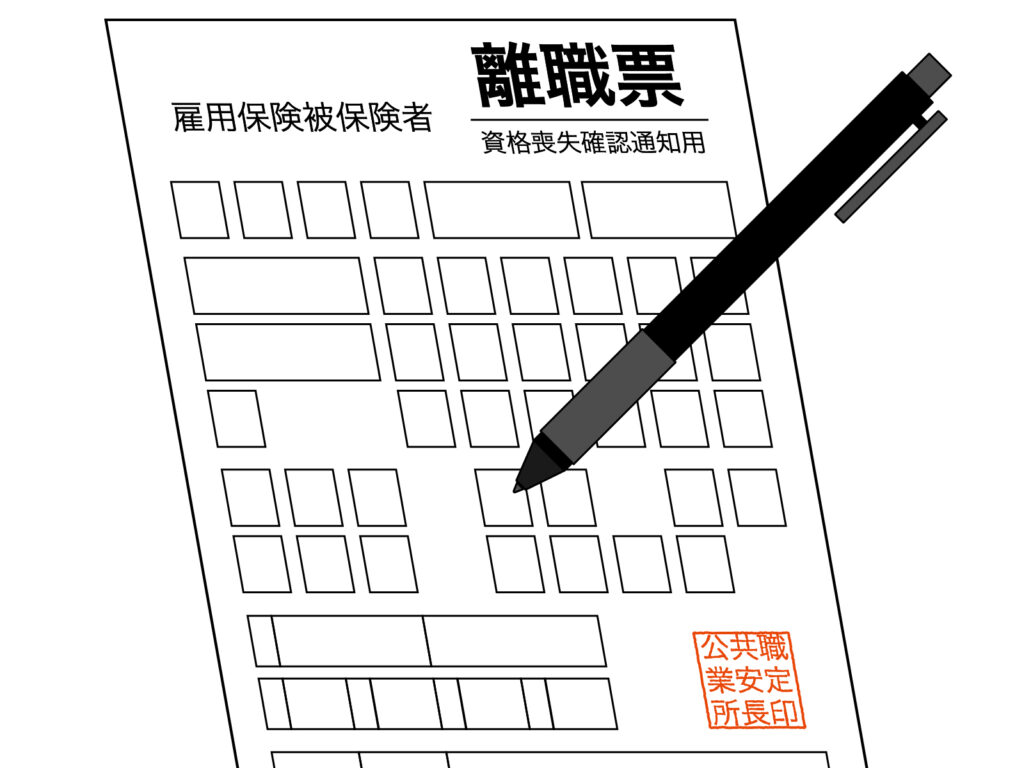

コメント